J.PRESS 120th anniversary limited edition
BOTANICAL garment dye
時代を超えて受け継がれる価値。
トラディショナルというサステナビリティに、
日本の“技”を重ねて
Text by mikiko TAMAKI
Photo by kenta SASAKI


アメリカ・ニューヘブンにてJ.PRESSが誕生して、今年で120年。記念すべきアニバーサリーイヤーに、ここ日本からJ.PRESSメンズが世に送り出したのが、「ボタニカルダイ・シリーズ」だ。
ブランドが守り続けてきたトラディショナルデザインに新たな表情を添えるのは、天然染料を用いた“製品染め(ガーメントダイ)”。染色を担う染工所「一陽染工」ではこの日、完成間近のサンプルを用いた最終調整が行われていた。


クラフトマンシップが息づく、120年目のトラディショナル
冬の柔らかな光が差し込む、昼下がりの染工所。大型機械が轟音をあげるその片隅で、小さなドラムのなか一枚のブルゾンがくるくると回りながら泳いでいた。
「いまちょうど、サンプルを使った染色の最終テストをしているところです」
そう話すのは、一陽染工社長・新木一一さん。
「ビーカー(染色試験)だけで各色最低5回。ゆらぎの出やすい天然染料で、ご希望の色にムラなく美しく染めるための数々の調整を経て、ようやくここまできました」と、晴れやかな笑顔で私たちを出迎えてくれた。



イギリスのハダースフィールド、イタリアのビエラと並び、「世界3代毛織物産地」にも数えられる愛知県・尾州地域。数多くのテキスタイル関連工場がひしめくこの地で昭和58(1983)年に創業した一陽染工は、数々の特殊染色の技術開発で、業界から一目置かれる存在だ。
先染めした糸を使用し、パッチワークのような多色織物に仕上げる「カラーインディゴ加工」や、生地の表裏を異なる色で仕上げる「ウノ・デュエ加工」など、数多くの新技術で世界のファッションに新たな潮流をもたらしてきた同社。
じつは、今回取り組むボタニカルダイについても、20年ほど前から研究を続けている。
「当時、民藝的な流れをくんだ草木染めのブームがあったのです。あくまでも作家性の高い、手工芸の一点ものが主でしたが、染めに関することですから私も気になって。(岐阜県)郡上からヒノキの葉をトラックいっぱいにもらって、染料を自分で抽出し染めるところから始めました。
たとえばヨモギなどの植物なら、収穫時期によって色の出方がまったく違ったり、びっくりするような色に仕上がったり。とても奥深く、探求しがいがある技術です」
一方で、ボタニカルダイは染料のロットによって色の出方が違うと言われるほど、一定の物量を安定的に染めるのが非常に難しい。このことから、多くのアパレルブランドでは長くこの技術が敬遠されてきたという事情もあるようだ。
いくらビーカーで試験を重ねても、現物を染あげるまで結果が見えないのがボタニカルダイの難しさ。しかも糸や反物よりもずっと凹凸の多い製品染めだ。決して簡単とは言えないオーダーだが、新木さんに迷いの色はない。
「たんに染めるだけなら、どなたでもできること。私たち染工所が手がけるなら、天然素材でもいかにムラなく、堅牢度※を高めて安定した色が出せるかを追求するのが仕事です」
※堅牢度:染色した生地の変色や色落ちのしにくさを表す尺度のこと
J.PRESSならではのサステナビリティを求めて
では、ブランドとしての製作サイドの想いはどうだろう。日本におけるJ.PRESSの歴史のなかで、ボタニカルダイを取り入れたのも、もちろん今回がはじめてのこと。120年というアニバーサリーイヤーになぜこの技術を選んだのか、デザイナーの池谷はこう語る。
「アイビーブームの一翼を担ってきたJ.PRESSというブランドが、120年目に伝えるべきメッセージはなにか。そう思いを巡らせるなかで、『サステナブル』というコンセプトが導き出されました。
ここでいうサステナブルとは、環境への配慮という意味合いだけではありません。テーラリングのブランドとしての原点に立ち返った、職人たちの手仕事を未来へとつなぐ意思を表すようなものづくりであるべきだと考えたのです」
天然染料を用いるという挑戦は、環境負荷の少ない持続可能な衣服生産への小さな一歩に。加えて、ガーメントダイならではの質感によって、一着の衣服に携わる多くの人々のクラフトマンシップという“気配”をまとわせることができたら──。そんな思いを込めて、ブランドのベースカラーとも言えるネイビーを中心にサックス、グリーンティ、そしてピンクの4色を展開。染料のベースにはログウッドやクチナシ、チャノキなどを用いることとなった。アイテム展開も、ブルゾンにTシャツと、いずれもブランドを体現するベーシックなものばかり。ただしもちろん、そのディティールには2022年ならではの洗練と軽やかさが感じられる。
120年の歴史のなか、リリースされてきたアイテムたちが、時代を象徴するヴィンテージとして愛されてきたように。今回のシリーズもまた、2022年の今だからこそ生まれた一着として愛され、受け継がれていく未来を思い描いてしまう。
10年、20年後の未来にも愛される一着に
父のクローゼットにかけられていたブレザー。母が大事そうにクリーニングから持ち帰ってきたダッフルコート。まぶしいようないつかの光景を記憶の片隅に持つのはきっと、私だけではないだろう。J.PRESSのアイテムに袖を通すとき、私たちは「過去からつながる現在」という長い時間軸をまとっているとも言える。絶えず変化し続け、移ろう時代のなかで、安心感にも通じる心地よさを与えてくれる、その体験。ここに「未来」というまなざしを加えたのが、ボタニカルダイシリーズなのではないだろうか。

「『親から子へと受け継ぐ服』は、J.PRESSの古くからのコンセプトの一つ。それができるデザインの普遍性や品質のたしかさもまた、サステナビリティにつながるもの。一陽染工のみなさんのお力を借りたからこそ、その思いを実現することができました」
池谷の言葉を受け、新木さんは最後にこう話した。
「職人が自分の仕事に惚れる、その熱が込められた服には、説得力という力が宿るものだと思っています。そういう仕事を一つでも二つでも重ねていけることが、私たち職人の一番の喜びなんです」



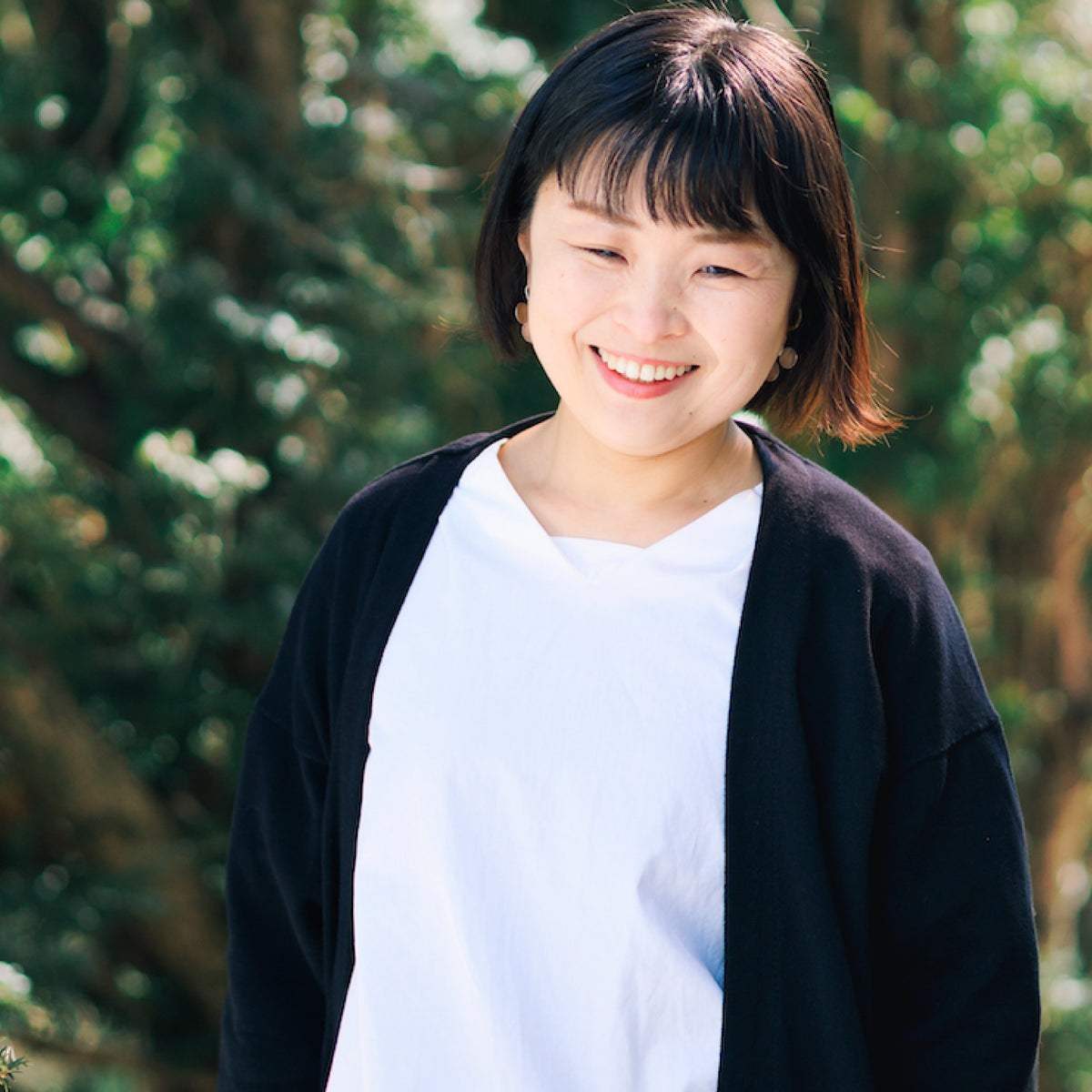
玉木美企子
TAMAKI Mikiko
1977年東京生まれ。雑誌編集、コピーライティング、放送作家等を経てフリーランスに。2015年に拠点を南信州に移し、食・農・暮らし・子どもを主なテーマに編集ライティングを行っている。日本在来種みつばちの養蜂を行う「養蜂女子部」の一面も。

佐々木健太
Kenta SASAKI
1983年長野県生まれ。東京綜合写真専門学校卒業後、スタジオアシスタント、広告制作会社アシスタントを経てフリーランスへ。結婚を機に長野県中川村へ拠点を移す。
